溶接工の仕事とは?具体的な仕事内容や働く魅力、向いている人を紹介
- 工場求人の仕事内容
2025/10/27

溶接工の仕事に興味を持っている方で、以下のような疑問を抱えていませんか?
「溶接工ってどのような仕事をするの?」
「資格やスキルは必要?未経験でもできる?」
「溶接工の仕事のやりがいや魅力は?」
溶接工とは、ものづくりに欠かせない技術職のひとつです。
もくもく作業が中心の製造職の中でも、自分の手でモノを作り上げる喜びや達成感を味わえる、やりがいのある仕事です。
本記事では、溶接工の給料相場や向いている人の特徴、未経験から目指す方法などを詳しく解説しています。
溶接工への就職・転職を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
プライム上場グループで
正社員として働きませんか?
ウィルオブでは製造現場で正社員として働いてくれる仲間を募集しています。資格もスキルも学歴も不問。未経験から溶接工を目指す方でも安心して働ける配属先をご提案します。
また単身者用の社宅も用意しており、初回配属先(エリア)を選ぶことも可能です。
TOPICS
溶接とはどんな技術か?

基本的に、材料を加熱もしくは加圧して2つの材料を接合する技術です。
鉄だけでなく、アルミニウムやクロムなどの金属に加えて、プラスチックなどの樹脂も溶接することがあります。
溶接の種類は大きく分けて3つ
溶接には「融接」「溶接」「ろう接」の3種があります。
それぞれについて詳しく解説します。
融接
融接は、金属材料を高温で溶かして接合する一般的な溶接技術です。
加熱して溶融状態にした後、冷却することで一体化させます。
主な融接法には、電気アークを利用するアーク溶接、酸素とアセチレンの燃焼熱を使うガス溶接、高エネルギーレーザーで精密に接合するレーザー溶接があります。
強固な接合が可能なため、自動車や建築、造船など幅広い分野で活用されています。
圧接
圧接は、加熱せずに圧力を加えて金属を接合する技術です。
代表的な方法には、摩擦圧接と抵抗溶接があります。
摩擦圧接は部品同士を摩擦させて接合し、抵抗溶接は電流で加熱し圧力を加えます。
溶融せずに強固な接合ができるため、軽量部品や異種金属の接合に適しています。
ろう接
ろう接は、部材を溶かさずに低融点のろう材を溶かして接合する方法です。
ろう材が接合部に浸透し、化学的な結合を形成します。
比較的低温で作業できるため、母材の変形や損傷を抑えられます。
電子機器の基板や精密機械部品の接合に用いられ、銀ろうや銅ろうが使われます。
作業は容易ですが、高度な技術が必要です。
溶接工の主な仕事内容
溶接工の主な仕事内容は以下の4つです。
- 図面や仕様書の読み取り
- 溶接の段取り作業
- 溶接作業
- 溶接後の検査と修正作業
溶接工は、図面を読み解くところから溶接箇所の検査と修正まで、一連のプロセスを担います。
それぞれのプロセスを詳しく見ていきましょう。
1、図面や仕様書の読み取り
溶接工は、まず図面や仕様書を丁寧に読み解き、溶接する場所や溶接方法、使用する金属の種類、厚さなどを正確に把握します。
図面には溶接記号と呼ばれる特殊な記号が記載されており、正確で安全な溶接作業を行う上で欠かせません。
作業現場は、自動車工場や造船所、建設現場、プラントなど多岐にわたりますが、図面や仕様書の読み取りはすべての溶接工に共通する重要な業務です。
図面を正しく理解できれば、溶接ミスを防ぎ、高品質な製品作りにつなげられます。
2、溶接の段取り作業
図面や仕様書の確認が終わると、次に溶接の準備に取りかかります。
使用する金属材料を適切な大きさに切断したり、溶接機やトーチなどの機器の調整したりなど、段取り作業は多岐にわたります。
また、溶接は高温や火花を扱う危険な作業でもあるため、安全かつ効率的に作業を進めるためにも、事前の準備は欠かせません。
例えば、アーク溶接では、溶接棒の種類や太さ、電流値などを適切に設定すると、溶接品質が向上できます。
加えて、溶接する材料の表面をきれいに清掃しておくと、溶接不良を防止できます。
3、溶接作業
溶接の作業方法は、以下のようにさまざまです。
- アーク溶接
- ティグ溶接
- マグ溶接
- ミグ溶接ガス溶接
溶接する金属の種類や厚さ、求める強度や精度、作業環境などに応じて最適な方法を選択します。
また、溶接作業は、火花や高温の金属による火傷など危険がともなうため、安全対策が欠かせません。
例えば、アーク溶接では、アーク光から目を保護するための遮光面や、火花から体を守るための保護具を着用する必要があります。
4、溶接後の検査と修正作業
溶接が完了したら、溶接箇所にひび割れや欠陥、歪みなどがないか、厳密に検査します。
検査方法は、目視検査だけでなく、X線検査や超音波検査などの非破壊検査を用いる場合もあります。
もし問題が見つかった場合は、グラインダーなどで溶接部を削ったり、再溶接を行ったりなどの修正作業が欠かせません。
最終的には、溶接部の外観を美しく仕上げるための研磨作業などを行い、製品の品質を確保します。
検査工程は、製品の安全性や信頼性を確保するために重要な工程です。
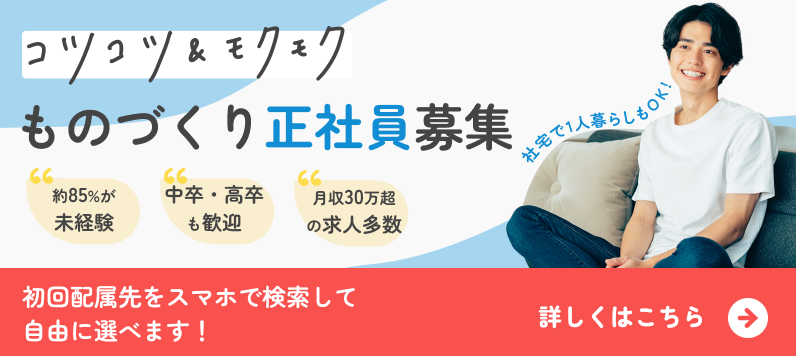
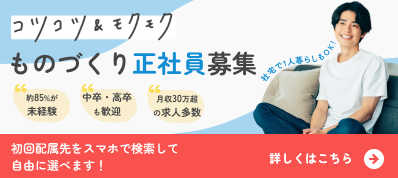
溶接工として働く3つのメリット・魅力

溶接工として働くことには、以下のようなメリットや魅力があります。
- 専門職を手につけられる
- 未経験からでも高収入やキャリアアップを見込める
- 需要が高く将来性がある
溶接工は、専門性や将来性などから、スキルを身につければ安定して働ける職業です。
それぞれのメリットや魅力を詳しく見ていきましょう。
専門職なので手に職をつけられる
溶接は専門的な技術と知識が必要な仕事です。
そのため、一度溶接のスキルを身につければ、一生涯キャリアとして活用できるでしょう。
また、溶接工は、製造業をはじめ、建設業、造船業、プラントなど、さまざまな業界で必要とされる職種です。
景気に左右されにくく安定した需要があり、年齢を重ねても転職しやすく、働き続けられます。
さらに、溶接工は独立して自分の工房を持つなど、将来のキャリアパスも広げやすいです。
日本溶接協会が実施する溶接技能者評価試験に合格すれば、自身の溶接技術を証明できるため、安定した稼働につなげられます。
未経験からでも高収入やキャリアアップを見込める
溶接工は、未経験からでも始められる仕事です。
最初は覚えることも多く、技術を習得するには努力が必要ですが、経験を積むにつれて着実にスキルアップできます。
実際に溶接工は、未経験で働き始めてから技術を身につける方も多いため、他業界からの転職も多い傾向があります。
また資格を取得したり、高度な溶接技術を習得できれば、高年収や現場監督や溶接技術指導者などのキャリアアップも可能です。
そのため、未経験の方で溶接工に興味がある方は、まずは実務で挑戦してみるのがおすすめです。
需要が高く将来性がある
溶接は機械化が進んでいますが、人の手でしかできない業務も多いため需要が高い業務です。
近年は、特にインフラ整備やプラント建設などの需要が高まっており、溶接工の需要は増加しています。
また、高齢化による熟練溶接工の減少も相まって、若手溶接工の育成が急務のため、若手人材は未経験でも採用されやすくなっています。
さらに、未経験からでも技術を身につけると、市場価値の高い人材になることも可能です。
将来的に職を失うリスクや転職できないリスクが低く、長期にわたって活躍できます。
溶接工の給料相場はどのくらい?
| 雇用形態 | 給料相場 |
|---|---|
| 正社員 | 平均年収419万円 |
| 派遣社員 | 平均時給1,350円 |
| アルバイト・パート | 平均時給1,197円 |
溶接工の全国の平均年収は約419万円とされています。(2025年9月現在)
しかし、溶接工は経験とスキルがものを言う仕事です。
資格や経験がある溶接工の中には、年収600〜1,500万円程度を稼いでいる人もいます。
経験年数や、その経験んから自然に身につく技術をもとに資格取得をしていくことも可能なので、1年~2年後のキャリアアップを見通すと、未経験で飛び込んで損のない職業と言えます。
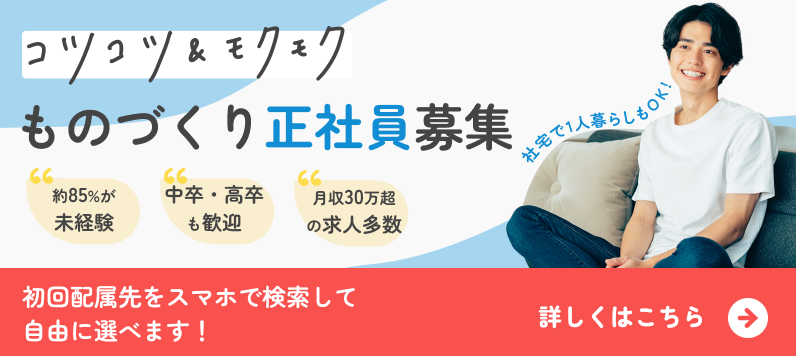
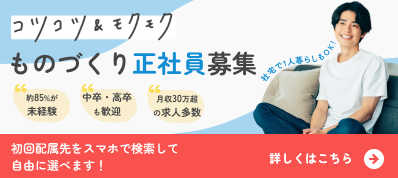
溶接工として働くことに向いている人の特徴

溶接工に向いている人の特徴は以下の通りです。
- 繊細な作業が好きな人・得意な人
- 集中力が高く、長時間作業が苦にならない人
- 体力や筋力に自信がある人
- ものづくりが好きな人
- 専門性を磨きたい人
溶接は、溶接棒の角度や送り速度、電流の強さなどを細かく調整しながら金属を溶かして接合するため、細かい作業でも集中して取り組める人に向いています。
また、大きな構造物の溶接では、何時間も続けて同じ姿勢で作業を行う場合も少なくありません。
集中力を切らさずに、長時間同じ作業を続けられる忍耐力が必要です。
加えて、重い溶接機材を運んだり、屋外や高温の環境で働くこともあるため、体力も求められます。
その他、ものづくりが好きな人や、常に新しい技術や知識を学び、専門性を高めていきたい人も、溶接工に向いています。
溶接工として働く際に役立つ5つの資格

溶接工でのキャリアで役立つ資格は以下の5つです。
- アーク溶接作業者
- ガス溶接作業者
- ボイラー溶接士
- ステンレス鋼溶接技能者
- 溶接管理技術者
上記の資格を取得していると、就職や転職、キャリアアップ、収入アップに有利に働きます。
それぞれの資格を詳しく見ていきましょう。
アーク溶接作業者
アーク溶接作業者の資格は、安全衛生特別教育規程に基づく特別教育を修了すると取得できます。
アーク溶接作業者を取得すると、多くの場面で使われるアーク溶接の知識や技術を証明できます。
また、18歳以上であれば誰でも受講可能で、比較的取得しやすい資格であるため、溶接の入門資格としておすすめです。
ガス溶接作業者
ガス溶接作業者の資格は、ガス溶接技能講習を修了すると取得できます。
そのため、アーク溶接作業者と並んで溶接工の入門資格のような位置付けの資格です。
ガス溶接は比較的低温で溶接できるため、薄板の溶接や精密な作業や可燃性ガスと酸素を使った金属の溶接、加熱作業に携われるでしょう。
アーク溶接と同様に、溶接の基礎を学ぶ上で重要な資格です。
参考:公益財団法人 安全衛生技術試験協会(ガス溶接作業主任者の紹介)
ボイラー溶接士
ボイラーや圧力容器は高い圧力を扱うため、溶接の品質が安全に直接関わる重要な役割としてボイラー溶接士の資格は欠かせません。
また、「普通ボイラー溶接士」と「特別ボイラー溶接士」の2種類があり、それぞれ受験資格が異なります。
普通ボイラー溶接士は、1年以上の溶接作業経験が受験資格です。
一方特別ボイラー溶接士は、普通ボイラー溶接士取得後、1年以上のボイラーまたは第一種圧力容器の溶接作業経験が必要です。
なお、筆記試験と実技試験に合格する必要があり、難易度が少し高いため、試験勉強や実技試験に向けた準備も欠かせません。
参考:一般社団法人 日本ボイラ協会(ボイラー溶接士免許の取得について)
ステンレス鋼溶接技能者
ステンレス鋼溶接技能者は、ステンレス鋼の溶接に関する専門的な知識と技能を証明する資格です。
ステンレス鋼は、耐食性や耐熱性に優れているため、さまざまな産業分野で利用されているため、ステンレス鋼溶接技能者の資格は高い需要があります。
また、JIS規格を基準にして判断された一定レベルの知識・技能を持っている証明にもなるため、溶接工求人を探している方にもおすすめの資格です。
溶接管理技術者
溶接管理技術者は、溶接施工計画の作成や溶接作業の監督、品質管理など、溶接に関する幅広い知識と技術を必要とする資格です。
溶接管理技術者は、溶接のスペシャリストとして、現場を統括する重要な役割を担います。
等級は特別級、1級、2級の3つがあり、上位の等級ほど高度な知識と経験が求められます。
また、受験するためには学歴や職務経験年数が求められるため、受験するのも簡単ではありません。
ただし、取得できれば、高いスキルと知識、経験の証明になり、キャリアアップや年収アップにつなげられます。
溶接工を未経験から目指すための方法
溶接工の仕事は、正社員・派遣ともに資格なし・未経験でも働くことができる求人が多くあります。
そのため、興味のある方はまずそういった求人に応募し、働いてみましょう。
そこで溶接の種類や溶接機器の操作方法、安全管理など実践的なスキルを身につけられます。
一方、専門学校や職業訓練校で学ぶこともできます。
職業訓練校の中には、ハローワークと連携して求職者支援訓練を実施しているところもあり、無料で受講できる場合もあります。
まず働くにしても学校などで学ぶにしても、資格の取得を目指しましょう。
それによってキャリアアップ・収入アップに繋げられます。
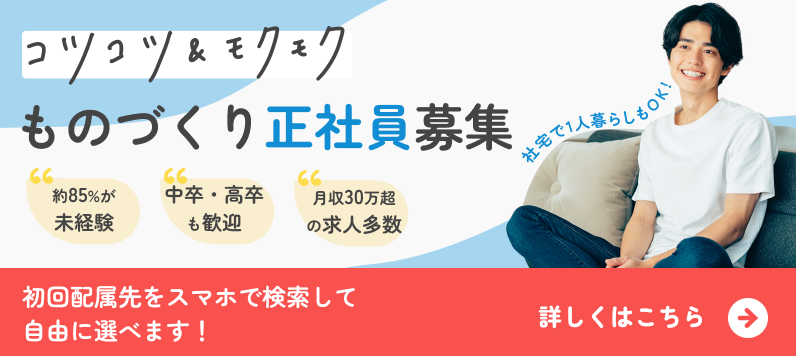
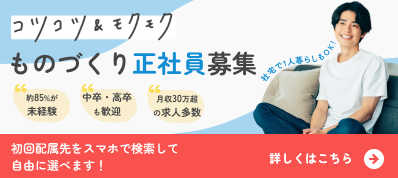
溶接工の仕事に関するよくある質問
溶接工の仕事内容は何ですか?
溶接工は、金属同士を接合する作業を行います。主に工場や建設現場で、アーク溶接やガス溶接などの技術を使って製品や構造物を製造・修理します。
詳しくは溶接工の主な仕事内容で解説しています。
溶接工の給料はどれくらいですか?
地域や経験によりますが、月収20万円〜35万円程度が一般的です。夜勤や残業がある現場ではさらに収入が上がることもあります。
詳しくは溶接工の給料相場はどのくらい?で解説しています。
溶接工は未経験でもなれますか?
はい、未経験から始められる求人も多数あります。入社後に資格取得支援や研修制度が用意されている企業もあります。
詳しくは溶接工を未経験から目指すための方法で解説しています。
溶接工に必要な資格はありますか?
必須ではありませんが、アーク溶接やガス溶接などの技能講習を受けておくと就職に有利です。実務経験を積みながら資格取得を目指す方も多いです。
詳しくは溶接工として働く際に役立つ5つの資格で紹介しています。
溶接工の仕事はキツいですか?
屋外や高温環境での作業もあり、体力を使う仕事です。ただし、職場によっては空調設備や安全対策が整っており、働きやすさが向上しています。
溶接工の仕事に関するまとめ
溶接工は、高度な技術を駆使してさまざまな製品や部品の製造に貢献する、ものづくりの中核を担う存在です。
近年、若手溶接工の減少により人材不足が深刻化しているため、企業からのニーズは高まっています。そのため、これから溶接工を目指す方、転職を考えている方にはチャンスです。
本記事を参考に、溶接工でぜひキャリアアップを目指してみてください。
プライム上場グループで
正社員として働きませんか?
ウィルオブでは製造現場で正社員として働いてくれる仲間を募集しています。資格もスキルも学歴も不問。未経験から溶接工を目指す方でも安心して働ける配属先をご提案します。
また単身者用の社宅も用意しており、初回配属先(エリア)を選ぶことも可能です。
Related article関連記事
-
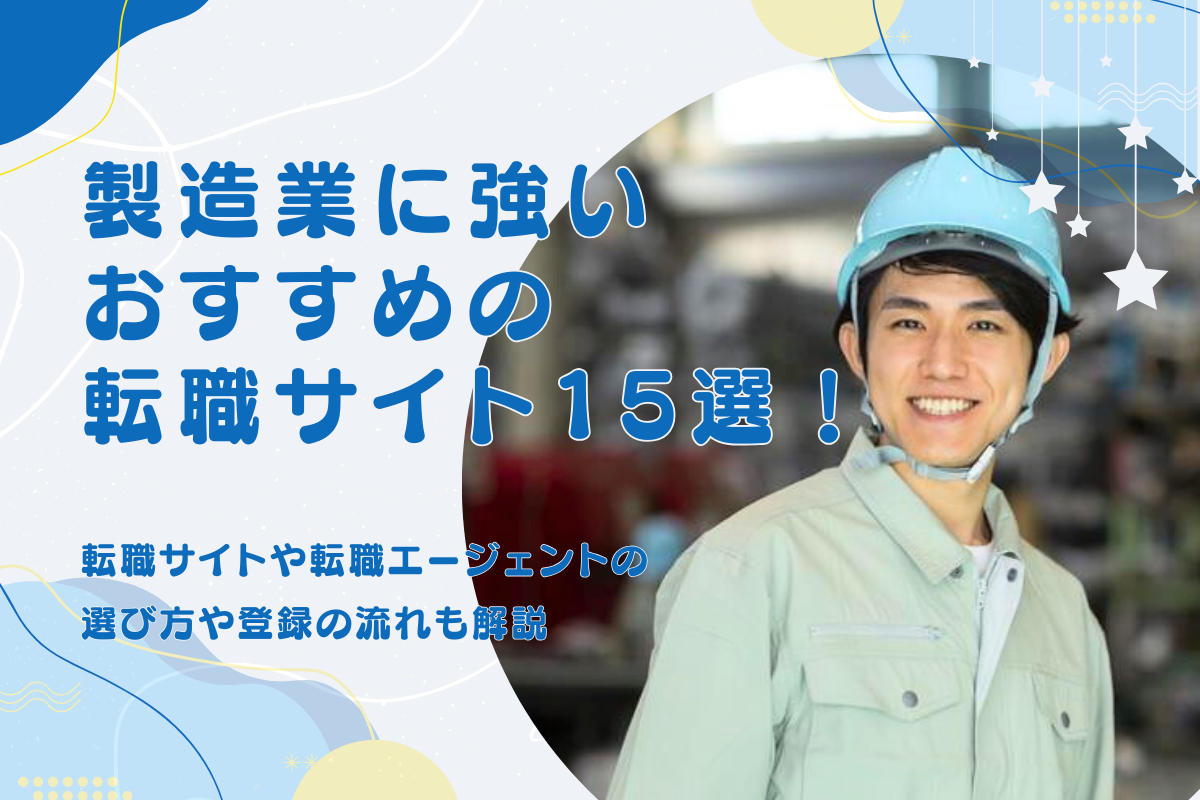
2026/01/05
【1月更新】製造業・工場に強いおすすめ転職サイト・転職エージェント15選!選び方や登録の流れも解説
-

2025/09/05
製造業は女性が働きやすい?おすすめの工場と女性が働くメリット
-

2025/06/20
工場勤務の正社員はきつい?その理由や正社員になるメリットと注意点
-

2026/01/05
【1月更新】軽作業に強いおすすめ派遣会社15社を比較!人気の仕事や軽作業のメリット・デメリットも紹介
-

2025/01/22
工場での「検査」の仕事ってどんな事をするの?仕事内容ややりがいも紹介
-

2025/03/03
倉庫内作業はきつい?具体的な仕事内容や職場環境もご紹介
-

2025/06/27
3勤務3休制とは?働き方とメリット・デメリット、向いている人の特徴
-

2025/04/28
食品工場の仕事を徹底解説!業務内容ややりがいとともに向き不向きも紹介
-
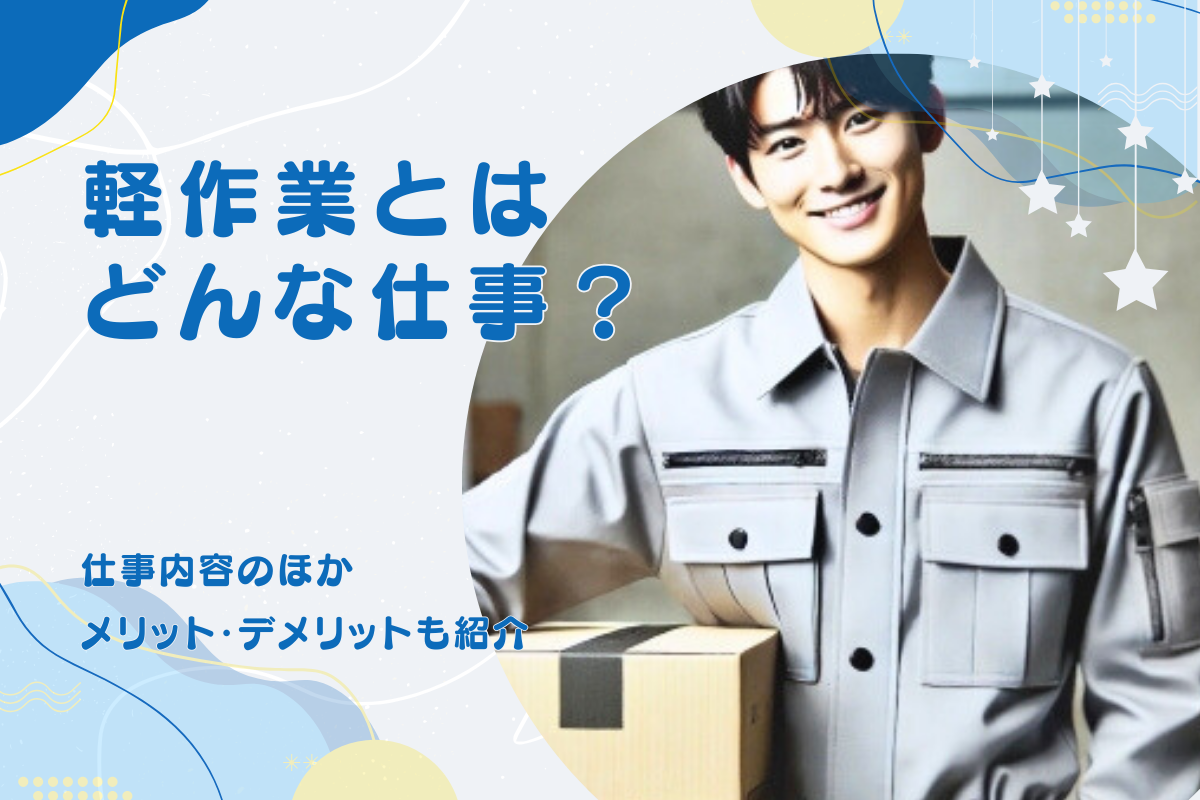
2025/05/16
軽作業とは?仕事内容や軽作業を選ぶメリット・デメリットなどを紹介
