製造現場で使われる「歩留まり」とは?言葉の意味や正しい使い方を伝授
- 工場の仕事に役立つ情報
2025/05/09

皆さんは「歩留まり」という言葉を聞いたことがありますか?
製造業特有の言葉であるため、一度も聞いたことがない、という方が大多数かもしれません。
「歩留まり」とは、一体何を指すのでしょう。
また、どんな時にどのように使用されるのでしょうか。
この記事では、これから製造業を志す方も予習しておきたい「歩留まり」について解説していきます。
プライム上場グループで
正社員として働きませんか?
ウィルオブでは製造現場で正社員として働いてくれる仲間を募集しています。キャリアアップの実績が豊富で、いずれは「工程リーダー」や「管理職」を目指したいという方に最適です。初回配属先を選ぶことができるので、エリアを重視して自宅からor条件を重視して社宅など多くの選択肢があります。少しでも気になる方は下記ボタンより詳細をご確認ください。
TOPICS
製造の現場でよく聞く「歩留まり」って?
こちら読み方ですが、「ぶどまり」と読みます。
「どまり」という響きが「止まり」を連想させることから、なんだか悪い事態のことを意味するのではないか、と思うかもしれません。
ですが、その意味はまったく異なります。
歩留まりとは、投入した原料や素材の量に対して、実際に得ることができた出来高の割合のことを指します。
そしてその出来高の割合を、歩留まり率と呼びます。つまり歩留まりは、成功した良い事態のことを意味します。
なにかをつくる時には不良品が発生するものです。
こうしたものは製品にならないため、ロスになってしまいます。
ロスになる=当然出来高の率が下がることになり、その率を表す時の日本独自の造語が、歩留まりなのです。
また、たとえ完成した製品でも不良が見つかった際は廃棄が免れず、利用可能率は下がってしまいます。
その割合についても歩留まりという言葉を用います。
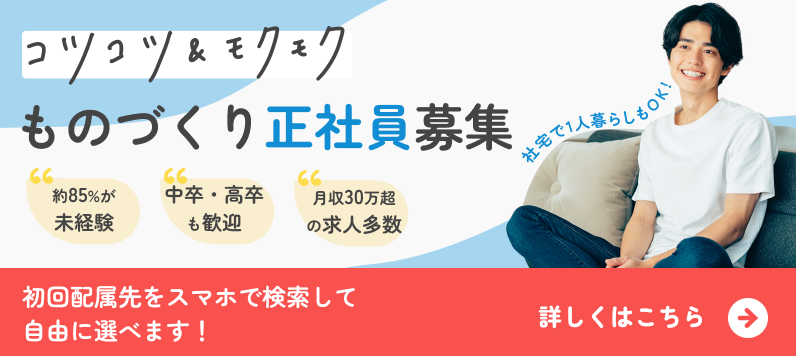
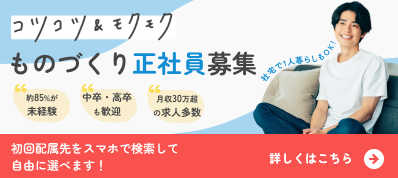
歩留まりの語源とは
歩留まりの意味は前述したとおりですが、なぜこのような言葉が生まれたのでしょうか。
実は歩留まりの「歩」は、「歩が悪い」などで使用される「歩」のことを指します。
この場合の「歩」は自分の取り分、という意味を指し、自分の取り分が留まる=利益が残っている、という意味で使われるようになりました。
「歩留まり(率)」の高い・低いとは?

では、製造の現場ではどのように歩留まりが使われているのでしょうか。例を挙げて分かりやすく説明します。
例
1)コストを削減するには、歩留まりを高くしなくてはいけない
→コストを削減するには、不良品を少なくしていかなければならない
2)●期においては、歩留まり率が20%向上しました
→●期においては、材料投入費に対して不良品の割合が20%減りました
3)歩留まりが低くて出荷に影響が出ています
→不良品が多くて出荷に影響が出ています
4)500円で販売する製品に材料費が400円もかかったなんて歩留まりが低かったなあ
→500円で販売する製品に材料費が400円もかかったなんてロスが多かったなあ(割に合わないなあ)
歩留まり率の計算方法
歩留まりを全体のうち成果として得られる割合と考える場合、次の式で求めることができます。
歩留まり率(%) = 実際に得られた成果数 ÷ 全体数 × 100
この考え方を、製造業における「使用した原料に対する完成品の割合」や「生産した中での良品の割合」に当てはめると、それぞれ次のように表せます。
▽使用原料に対する完成品の割合
歩留まり率(%) = 完成品の個数 ÷ 投入した原料の個数 × 100
▽生産した中での良品の割合
歩留まり率(%) = 良品の個数 ÷ 完成品の個数 × 100 = 良品率(%)
また、これらの式を組み合わせることで「投入した原料に対して得られた良品の割合」を歩留まりとして定義することも可能です。
たとえば、原料投入に対する完成品率が90%で、生産品に対する良品率が50%だった場合、100個の原料から90個の完成品ができ、そのうち良品は45個となります。
この場合、原料投入に対する良品の歩留まり率は45%となります。
歩留まり率から原材料数や原材料費を計算できる
歩留まり率を活用することで、目標とする生産数に対して必要となる原料の量を算出できます。
必要原材料数 = 目標生産数 ÷ 歩留まり率(%)
例えば、歩留まり率が75%の製品を150個作りたい場合、必要となる原料数は200個(=150÷75%)となります。
さらに、次の式を使えば、歩留まり率をもとに原材料コストを計算することも可能です。
原材料コスト = 1kgあたりの単価 ÷ 歩留まり率(%) × 必要なkg数
例えば、1kgあたり1,200円の牛肉を使い、歩留まり率75%でハンバーグを製造する場合、30kgの製品を作るための原材料コストは48,000円(=1200÷75%×30)となります。
製造現場での歩留まりの改善方法
まずは不良が出る原因を究明する
歩留まりの原因を調べる際に役立つフレームワークが「5M+1E」です。
これは、不良の発生要因を6つのカテゴリーに分けて考える手法で、それぞれ次の頭文字を指します。
- Man(人)
- Machine(機械・設備)
- Method(作業方法)
- Material(原材料・資材)
- Measurement(測定・検査)
- Environment(作業環境)
製造ラインで不良が多発している場合、この「5M+1E」の視点から各要素をリストアップしていくと、隠れた課題やボトルネックが明らかになることがあります。
歩留まりの向上を目指すうえで、ぜひ覚えておきたい基本的な考え方です。
適切な目標設定
歩留まり率は、基本的に高いほど望ましいとされています。
だからといって常に100%を目指せばよいというわけではありません。
最初から「歩留まり率を100%にする」と掲げても、現実味がなく、現場の納得や協力を得にくくなるでしょう。
そのため、段階を追って目標を設定し、少しずつ歩留まり率を改善していくことが効果的です。
この際のポイントは、目標を明確かつ具体的に決めることです。
単に数値目標を示すだけでなく、それを実現するための具体策や、達成までの期限を設定することが成功のカギとなります。
たとえば、歩留まりが下がっている原因が作業者の技術的な課題だとしたら、スキル向上のための研修を実施する必要があります。
そして「研修の実施により、1か月以内に歩留まり率を10ポイント向上させる」といった形で、より具体的な目標を掲げると良いでしょう。
歩留まりについてよくある質問
歩留まりとは何ですか?
歩留まりとは、投入した原料や生産数に対して、実際に使える成果や良品がどれだけ得られたかを示す割合のことです。製造業をはじめ、食品加工やIT業界でも使われる指標です。
詳しくは製造の現場でよく聞く「歩留まり」って?をご覧ください。
歩留まり率はどのように計算しますか?
歩留まり率は、成果数(または良品数)を全体数で割り、100をかけて計算します。例:歩留まり率(%) = 良品数 ÷ 完成品数 × 100
詳しくは歩留まり率の計算方法をご覧ください。
歩留まりを改善する方法はありますか?
歩留まりを改善するには、作業者のスキル向上、設備の点検・修理、原材料の品質管理、作業方法の見直しなどが有効です。5M+1Eの視点で原因を調べることも効果的です。
詳しくは製造現場での歩留まりの改善方法をご覧ください。
歩留まりと良品率の違いは何ですか?
歩留まりは、原料や投入数に対する成果の割合を指し、良品率は生産した完成品の中で不良がなく使える製品の割合を示します。使われる場面によって意味が少し異なります。
最後に
歩留まりとは不良品ではなく良品のことを指し、歩留まり率(良品ができる割合)の向上は、製品を製造している側にやりがいを与えてくれるとともに会社の利益にもつながります。
とりわけ製造業の基本は、なるべくロスをなくすことが重要です。
不良品を少なくすることで廃棄のコストも削減されるし、廃棄する時に使われるエネルギーの削減にもつながります。
その指標とも言える歩留まり、歩留まり率という言葉とその意味をしっかり理解して、今後の仕事はもちろん、普段の生活にも役立てていただければと思います!
プライム上場グループで
正社員として働きませんか?
ウィルオブでは製造現場で正社員として働いてくれる仲間を募集しています。キャリアアップの実績が豊富で、いずれは「工程リーダー」や「管理職」を目指したいという方に最適です。初回配属先を選ぶことができるので、エリアを重視して自宅からor条件を重視して社宅など多くの選択肢があります。少しでも気になる方は下記ボタンより詳細をご確認ください。
Related article関連記事
-
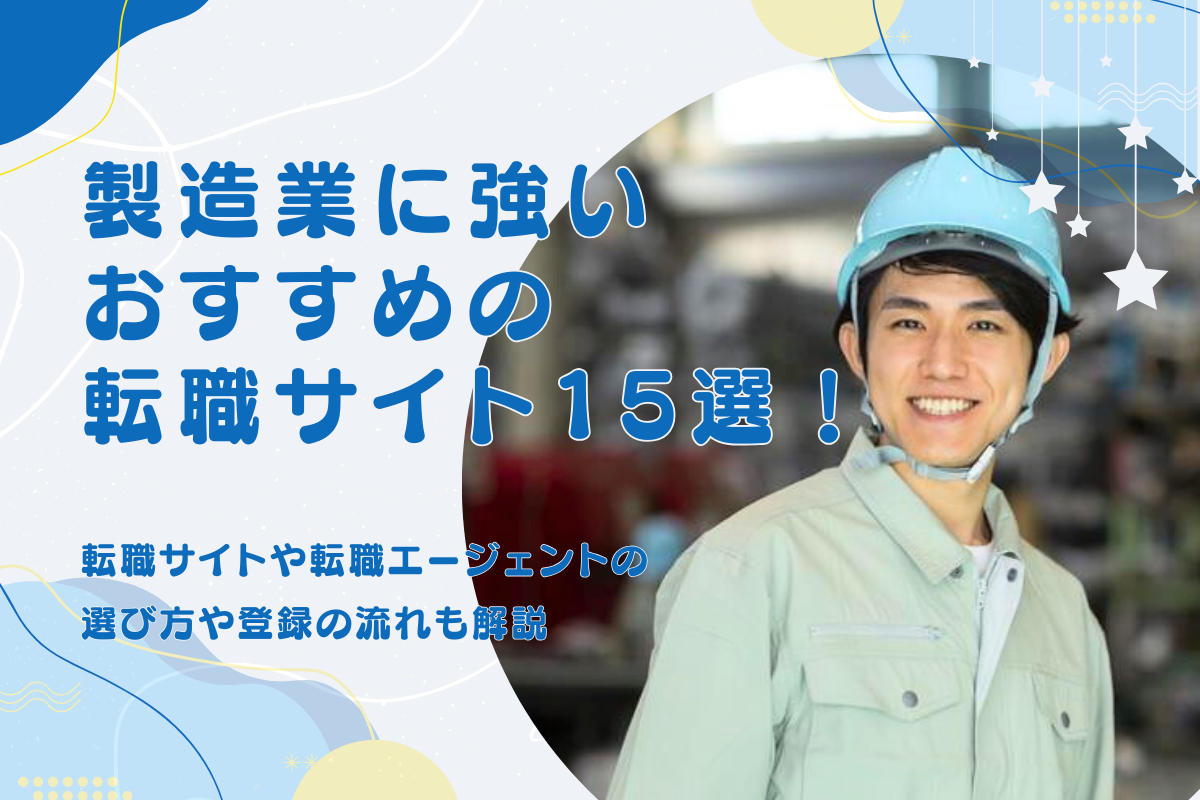
2026/01/05
【1月更新】製造業・工場に強いおすすめ転職サイト・転職エージェント15選!選び方や登録の流れも解説
-

2025/09/05
製造業は女性が働きやすい?おすすめの工場と女性が働くメリット
-

2025/06/20
工場勤務の正社員はきつい?その理由や正社員になるメリットと注意点
-

2026/01/05
【1月更新】軽作業に強いおすすめ派遣会社15社を比較!人気の仕事や軽作業のメリット・デメリットも紹介
-

2025/01/22
工場での「検査」の仕事ってどんな事をするの?仕事内容ややりがいも紹介
-

2025/03/03
倉庫内作業はきつい?具体的な仕事内容や職場環境もご紹介
-

2025/01/22
金属加工の仕事はきつい? そう言われる理由や仕事内容、向いている人を解説
-

2025/01/17
工場のマシンオペレーターとは?仕事内容や向き・不向きも紹介
-
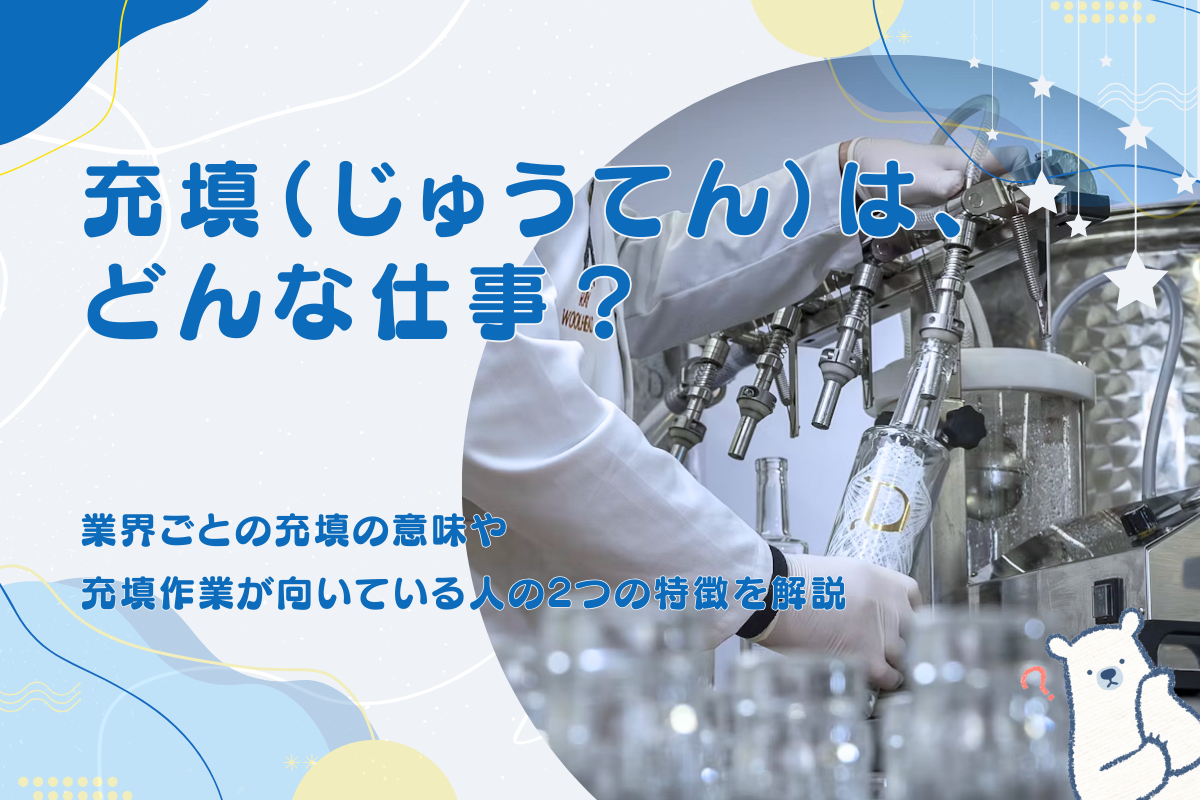
2025/05/23
充填とは?業界ごとの充填の意味や充填作業が向いている人の2つの特徴を解説
