3勤務3休制とは?働き方とメリット・デメリット、向いている人の特徴
- 工場での働き方
2025/06/27

3勤務3休制とは、3日間勤務した後に3日間休日を取るシフト制で、主に工場の製造ラインなどで採用されています。
年間休日が多い魅力がある一方で、生活リズムの乱れなどのデメリットに注意が必要です。
この記事では、3勤務3休制の基本的な働き方から、メリット・デメリットなど網羅的に解説します。
3勤務3休制で働くか迷っている方は、ぜひご参考ください。
プライム上場グループで
正社員になりませんか?
ウィルオブでは、こつこつ&もくもく作業が中心のものづくり正社員を募集しています。学歴や資格は必要ありません。研修が充実しているので未経験の方も安心してスタートできます!応募前に電話相談も可能なので気になる方は下記ボタンからぜひチェックしてみてください。
TOPICS
3勤務3休制とは?
3勤務3休制は、3日働いて3日休む勤務形態で、月(年)の半分は休日であり、休みが多いのが特徴です。
一般的に日勤と夜勤を繰り返すシフトを組む場合が多く見られます。
具体的には、日勤を3日行い3日休む、夜勤を3日行い3日休むなどのスケジュールが挙げられます。
24時間稼働が必要な工場やインフラ関連の施設で採用されている制度で、長時間勤務の代わりにまとまった休日を確保できる働き方です。
3勤務3休制で働く4つのメリット

3勤務3休制には、一般的な働き方にはない以下4つのメリットがあります。
- 休日が多くプライベートの時間を多く取れる
- まとまった休日を取れる
- 通勤ラッシュを避けられる
- 副業の時間も確保できる
上記のメリットが、自分のライフスタイルと合致するかどうか、一つずつ見ていきましょう。
休日が多くプライベートの時間を多く取れる
3勤務3休制の大きなメリットは、年間休日の多さです。
土日が休日の勤務の場合、月間の労働日数は20日程度で月間の休日は10日程度です。
しかし、3勤務3休制の場合は半分が休みになり、月間の労働日数も休日も15日程度あります。
これだけ休日が多いため、趣味や自己投資、家族との時間に費やせます。
仕事とプライベートのバランスを重視し、人生を豊かにしたいと考える人にとって、休日数の多さは魅力です。
心身ともにリフレッシュする機会が増え、仕事へのモチベーション維持にもつながるでしょう。
まとまった休日を取れる
3勤務3休制は平日にまとまった休日を取れるのが特徴です。
土日休みの場合、平日に連休を取ることは難しいですが、3勤務3休制なら平日に3連休を取りやすい傾向にあります。
また、まとまった休みを取れるため、旅行に行くことも可能です。
平日に休みを取れるため、交通費や宿泊費を抑えたり、混雑や渋滞を避けたりできるのもメリットの一つです。
さらに、役所や銀行での手続きもスムーズに済ませられるなど、日常生活での利便性も高まります。
通勤ラッシュを避けられる
3勤務3休制は一般的な労働者の通勤時間とずらすケースが多いため、通勤ラッシュを避けられるのもメリットです。
日勤でも朝のラッシュのピークを過ぎてから出勤できたり、夜勤であれば電車も道路も空いている時間帯に移動できたりします。
特に人口が集中する大都市圏で働く場合、満員電車や交通渋滞のストレスから解放されるメリットは計り知れません。
日々の通勤による心身の疲労が軽減され、より快適な毎日を送れます。
副業の時間も確保できる
3日間のまとまった休日を定期的に確保できる3勤務3休制は、副業やスキルアップに時間を使いたい人にとってもおすすめの環境です。
休日を丸ごと使って別の仕事に集中したり、資格取得のための勉強に打ち込んだりする時間を十分に確保できます。
例えば、Webデザインやプログラミングなどの新しいスキルを学ぶためのスクールに通うことも可能です。
将来のキャリアの選択肢を広げたい、あるいは収入の柱を増やしたいと考えている人にとって、この働き方は大きなチャンスとなります。
ただし、副業を始める前には、勤務先の就業規則で副業が許可されているかを確認してください。
3勤務3休制で働く4つのデメリット
魅力的なメリットがある一方で、3勤務3休制には事前に理解しておくべきデメリットもあります。
自分に合わない働き方を選んで後悔しないために、以下の4つの点を確認しましょう。
- 生活リズムが崩れやすい
- 労働時間が長くなりやすい
- 友人や家族と予定を合わせにくい
- 高収入を目指すことが難しい
上記のデメリットが自分にとって許容できる範囲内か、慎重に検討することが大切です。
生活リズムが崩れやすい
3勤務3休制では、日勤と夜勤を繰り返すため、生活リズムが崩れやすいのがデメリットです。
特に夜勤の際に睡眠不足に陥りやすく、身体的に疲労が蓄積する可能性が高くあります。
また、生活リズムの崩れによって、休日に眠気を感じ、時間の有効活用ができない恐れがあります。
せっかくの休日なのに、時差ボケのような状態で日中ずっと眠気を感じてしまい、時間を有効に使えないことも少なくありません。
生活リズムの乱れは、集中力の低下や免疫力の低下にもつながりかねないため、食事や睡眠の質を高めるなど、意識的な自己管理が大切です。
労働時間が長くなりやすい
3勤務3休制は労働時間が12時間程度と長くなりやすいのもデメリットです。
特に製造業で24時間稼働が必要な職場では、労働時間が長くなる傾向にあります。
週の半分が休みとはいえ、勤務日が3日間続くと、最終日には心身ともに疲労が蓄積することも珍しくありません。
休日が多いメリットは、出勤日の高い負荷と引き換えである点を理解しておく必要があります。
体力に自信がない人や、長時間の集中が苦手な人には厳しい働き方である可能性があります。
友人や家族と予定を合わせにくい
3勤務3休制は一般的な勤務形態と異なる休日の取り方のため、友人や家族との予定を合わせにくいのもデメリットです。
休日が平日になることが多いことはメリットですが、土日休みの方と休日が合いにくく、予定を合わせることが難しいです。
予定を合わせにくいことから、人間関係が希薄になる可能性や孤独を感じやすい点に注意が必要です。
人とのつながりを大切にしたい人にとっては、3勤務3休制は人間関係に影響を与えることを覚えておきましょう。
高収入を目指すことが難しい
収入面を重視する人にとっては、3勤務3休制は高収入を目指しにくい働き方の一つです。
1日の労働時間は長くても、年間の総労働時間でみると週5日勤務より短くなるケースがあるためです。
労働時間が短い分、基本給が低めに設定されていたり、そもそも残業が発生しにくく残業代での上乗せが期待できなかったりします。
そのため、一般的な勤務形態で働く同年代と比較して、年収が低くなる傾向があります。
休日の多さよりも収入の高さを優先したい人にとっては、希望する給与水準に届かない可能性がある点が大きなデメリットです。
3勤務3休制での勤務が向いている人の4つの特徴

ここからは、どのような人が3勤務3休制に向いているのかその特徴を紹介します。
- 平日が休日でも問題ない人
- 働き方の柔軟性を重視する人
- 収入よりも休日の多さを重視する人
- 体力に自信がある人
ご自身が上記の特徴に当てはまるか、自己分析の参考にしてみてください。
平日が休日でも問題ない人
世間一般の休日である土日にこだわらない人は、3勤務3休制に向いています。
平日が休みであれば、役所や銀行での手続き、病院の通院などをスムーズに済ませられます。
また、お店や観光地が比較的空いている平日に、自分のペースでゆっくりと時間を過ごせるのも魅力です。
逆に、家族や友人と週末を一緒に過ごすことを何よりも大切にしたい場合は、この働き方はあまりおすすめできません。
自分のライフスタイルと価値観を再確認することが重要です。
働き方の柔軟性を重視する人
決まった曜日や時間帯に縛られるのではなく、柔軟な働き方を求める人にとって3勤務3休制は魅力的な選択肢です。
日勤と夜勤を繰り返しながら、週の半分を休む独特なリズムは、型にはまらないライフスタイルを望む人にフィットします。
生活リズムが崩れやすいデメリットを乗り越え、日中と夜間の時間をそれぞれ有効活用したいと考える人にはぴったりです。
例えば、日中は趣味に没頭し、夜勤前の時間を使って勉強するなど、時間の使い方を自分でデザインできます。
副業やキャリアアップを目指す場合にも、この働き方は大きな強みとなります。
収入よりも休日の多さを重視する人
収入額よりも、自由に使える時間の多さを優先する価値観を持つ人にもおすすめです。
この働き方は年収がやや低くなる傾向がある一方で、年間休日数が多い明確なメリットがあります。
「給料は生活できるレベルで十分。それよりも趣味や旅行に使う時間をたくさん確保したい」と考える人には、理想的なワークライフバランスを実現できる働き方です。
人生の中で、お金と時間のどちらに重きを置くかを考えることが、働き方を選ぶ重要な判断基準になります。
体力に自信がある人
3勤務3休制は日勤と夜勤を繰り返すことや1日の勤務時間が長い傾向にあるため、体力面に自信がある方に向いています。
勤務日の負担に耐えられるだけの体力は必須条件です。
また、生活リズムが乱れやすく疲労が蓄積しやすいことからも、体力に自信がある方のほうが適しています。
ただし、体力に自信がある方でも食生活や睡眠方法の工夫など、体調管理を怠らないように注意が必要です。
自分の体力を過信せず、しっかり自己管理を欠かさず行いましょう。
3勤務3休制に関するよくある質問
最後に、3勤務3休制に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめます。
3勤務3休制での工場勤務で有給は取れますか?
3勤務3休制でも、「入社から6ヵ月以上継続勤務している」「その期間の全労働日の8割以上出勤している」の2つの条件を満たせば有給の取得は可能です。
有給休暇は労働者の権利であり、勤務形態によって左右されるものではありません。
ただし、工場勤務の場合は、作業の流れに支障がでないよう、有給の取得希望から余裕を持って上司や同僚に相談し、計画的な取得を心がけることが大切です。
(参考: 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省)
工場での3勤務3休制の収入目安はどれくらいですか?
工場での3勤務3休制の収入目安は正社員で360万円〜500万円です。
国税庁の調査によると、製造業全体の平均年収は531万円(令和4年分)です。この数字と比較すると、3勤務3休制の収入はやや低めの水準にあることがわかります。
3勤務3休制は、休日が多い分、年間の総労働時間が短くなる傾向があるためです。
とはいえ、収入が低くなっても休日数を重視する方にとっては3勤務3休制がおすすめです。
(参考: 令和4年分 民間給与実態統計調査|国税庁)
工場の3勤務3休制でキャリアアップは可能ですか?
3勤務3休制の働き方でも、本人の意欲と努力次第でキャリアアップは十分に可能です。
例えば、多い休日を利用して資格取得のための勉強時間を確保できます。
フォークリフト免許や危険物取扱者など、現場で役立つ資格を取れば、任される仕事の幅が広がり、昇進や昇給につながる可能性があります。
企業によっては研修制度や資格取得支援制度が用意されている場合もあるため、積極的に活用し、スキルを磨いていきましょう。
3勤務3休制の働き方はどの業種で採用されていますか?
3勤務3休制は、24時間365日の連続稼働が求められる業種、特に製造業の工場で多く採用されている勤務形態です。
具体的には、半導体工場、自動車部品工場、食品工場などが挙げられます。
そのため、もし3勤務3休制で働きたいのであれば、製造業や工場の求人情報を中心に探すのが効率的です。
工場勤務の正社員は、安定した雇用や収入、充実した福利厚生などのメリットも期待できます。
未経験からでも挑戦できる求人も多いため、新たなキャリアを考えている方にもおすすめです。
3勤務3休制についてのまとめ
3勤務3休制は、3日働いて3日休むシフト制勤務で、年間休日が多くプライベートの充実や副業に適した働き方です。通勤ラッシュを避けやすく、平日休みの利便性も魅力です。
一方で、日勤と夜勤の交代による生活リズムの乱れや、労働時間の長さ、収入面の伸び悩みといったデメリットも存在します。
体力に自信があり、柔軟な働き方を求める人に向いていますが、自身の価値観とライフスタイルに合うか慎重に検討することが重要です。
プライム上場グループで
正社員になりませんか?
ウィルオブでは、こつこつ&もくもく作業が中心のものづくり正社員を募集しています。学歴や資格は必要ありません。研修が充実しているので未経験の方も安心してスタートできます!応募前に電話相談も可能なので気になる方は下記ボタンからぜひチェックしてみてください。
Related article関連記事
-
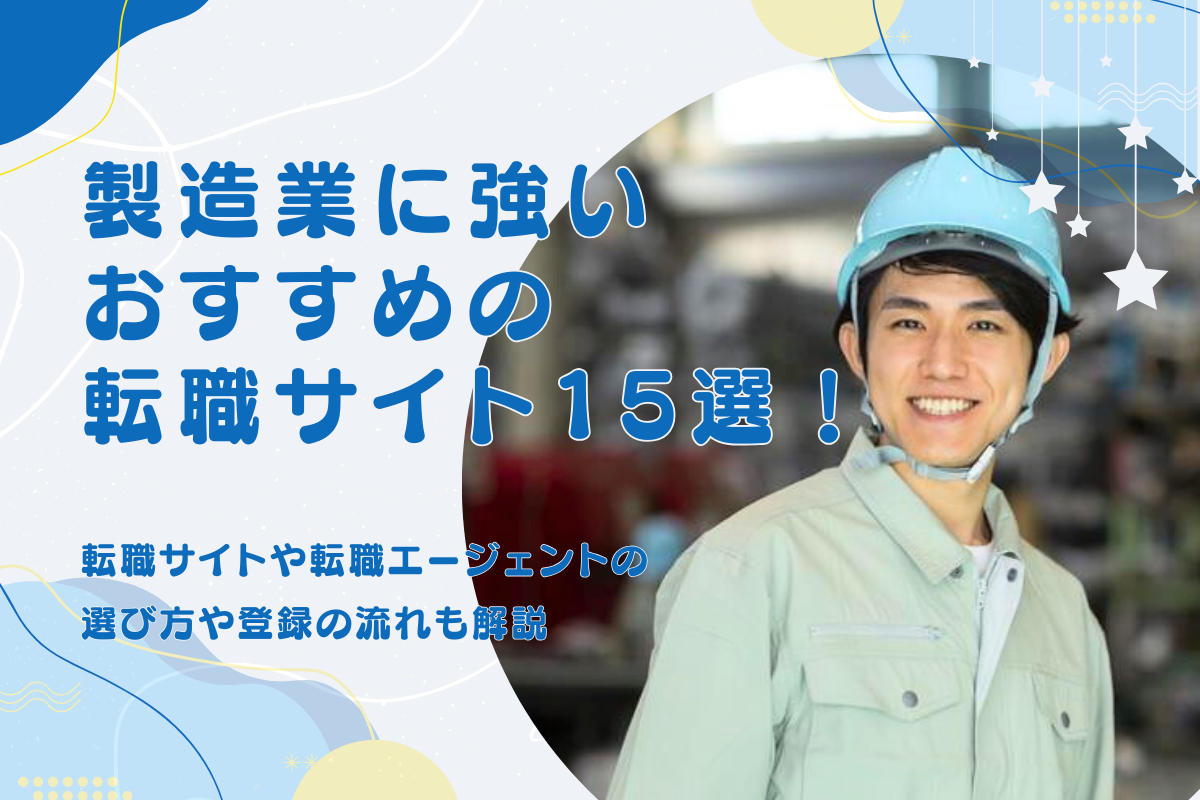
2026/01/05
【1月更新】製造業・工場に強いおすすめ転職サイト・転職エージェント15選!選び方や登録の流れも解説
-

2025/09/05
製造業は女性が働きやすい?おすすめの工場と女性が働くメリット
-

2025/06/20
工場勤務の正社員はきつい?その理由や正社員になるメリットと注意点
-

2026/01/05
【1月更新】軽作業に強いおすすめ派遣会社15社を比較!人気の仕事や軽作業のメリット・デメリットも紹介
-

2025/01/22
工場での「検査」の仕事ってどんな事をするの?仕事内容ややりがいも紹介
-

2025/03/03
倉庫内作業はきつい?具体的な仕事内容や職場環境もご紹介
-
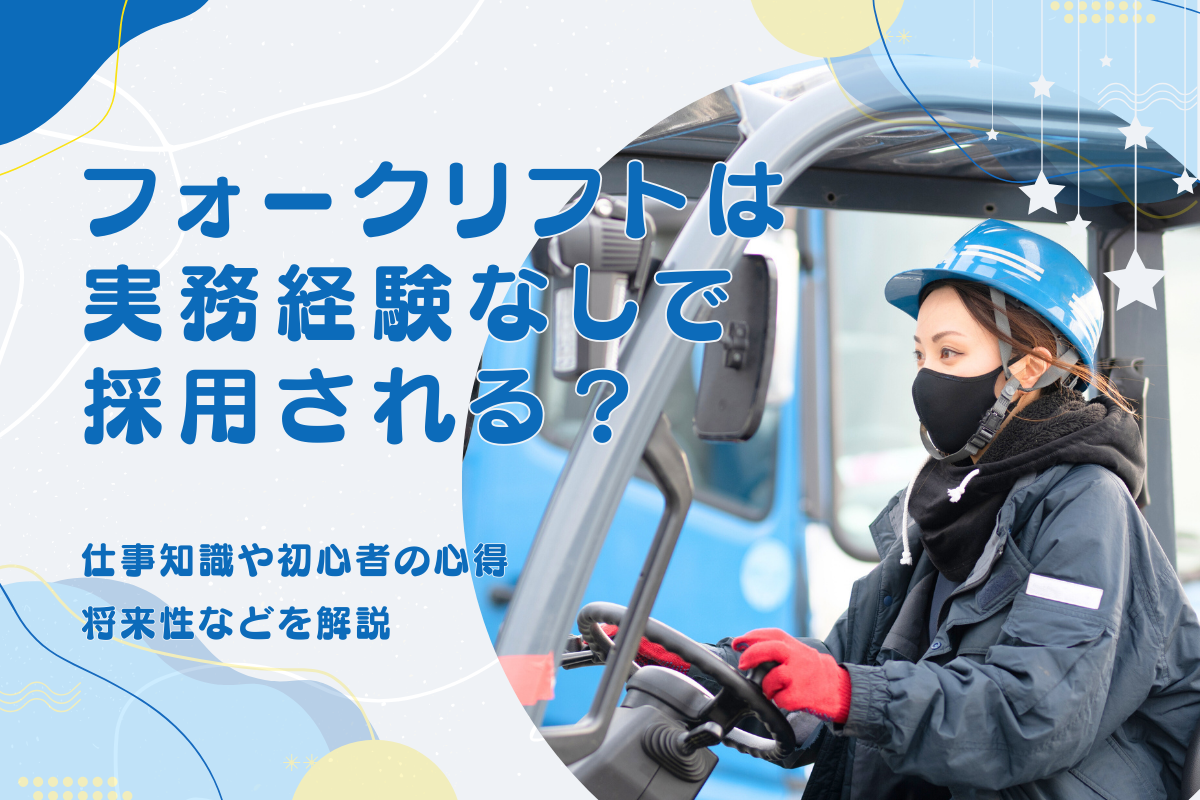
2025/04/21
フォークリフトは実務経験なしでOK?仕事知識や将来性も解説
-

2025/05/23
人と関わらない仕事14選!メリットやデメリット、仕事の探し方を解説
-
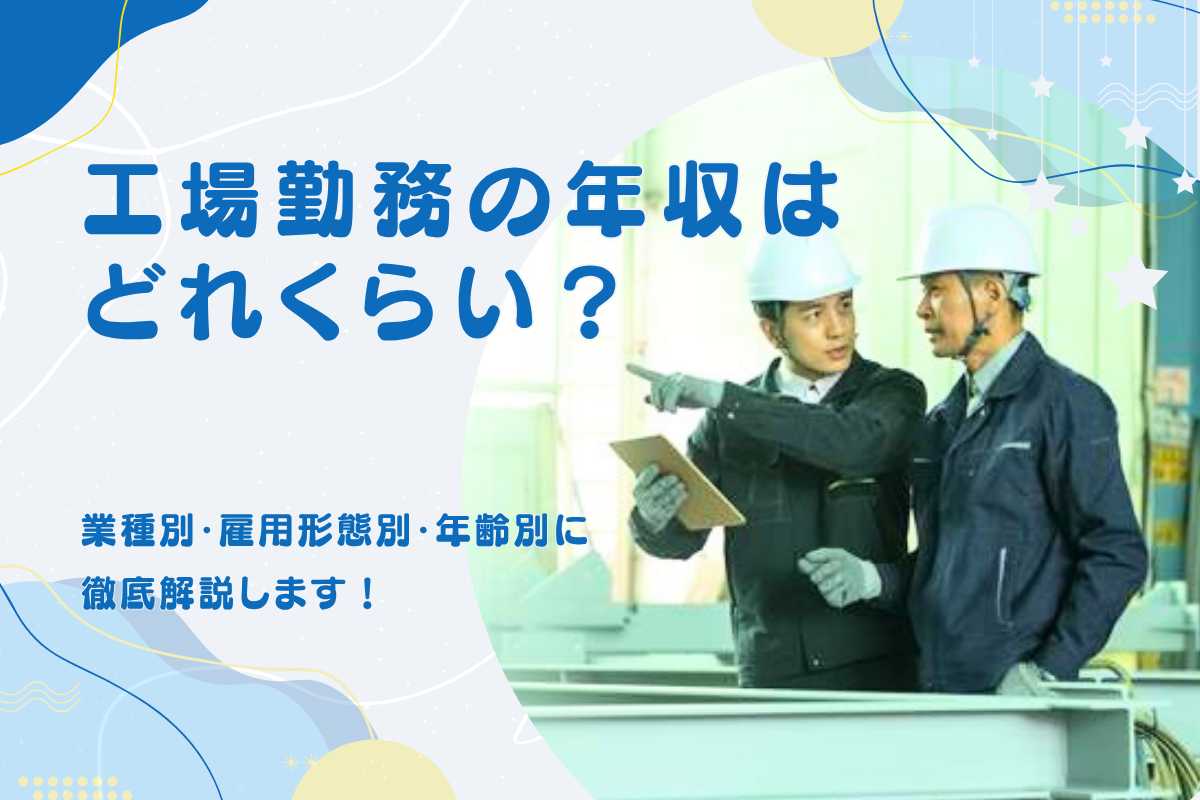
2025/06/12
工場勤務の平均年収はどれくらい?業種別・雇用形態別・年齢別に徹底解説

